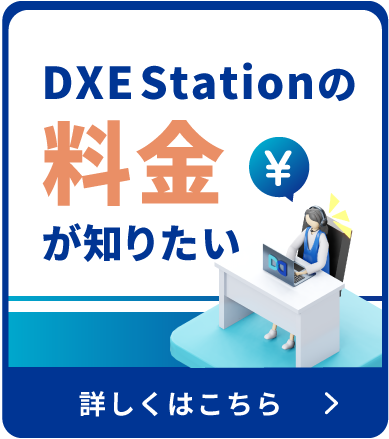汚泥は、産業廃棄物の中でも最も排出量が多く、その割合は全体の約4割を占めています。
事業活動に伴い発生する泥状の物質の総称であり、その性質は発生元によって大きく異なります。
この記事では、産業廃棄物における汚泥の定義や種類、泥土との違いといった基礎知識から、具体的な処理方法、リサイクルの手法、業者選定の注意点までを網羅的に解説します。
汚泥の適正な処理と管理は、企業のコンプライアンスと環境責任を果たす上で不可欠です。
目次
産業廃棄物における「汚泥」とは?
廃棄物処理法において、汚泥は「工場排水などの処理後に残る泥状のもの、及び各種製造業の生産工程で出る泥状のもの」と定義されています。
具体的には、事業活動から排出される、水分を多く含んだ泥状の廃棄物の総称を指します。
重要なのは、汚泥には含水率や粘性に関する明確な数値基準が存在しない点です。
そのため、見た目が泥状であれば、その成分や発生工程にかかわらず広義の汚泥として扱われる可能性があります。
適正な処理を行うためには、まず自社から排出される廃棄物が汚泥に該当するかを正しく判断することが第一歩となります。

汚泥と泥土(土砂)との違い
汚泥と泥土(土砂)は見た目が似ていますが、法的な扱いは全く異なります。
最も大きな違いは、汚泥が廃棄物処理法にもとづく「産業廃棄物」であるのに対し、泥土は基本的に廃棄物ではなく「有価物」として扱われる点です。
特に建設工事現場で発生する掘削土砂(建設発生土)は、他の工事で盛土材などとして再利用できるため、廃棄物には該当しません。
ただし、建設汚泥のように有害物質を含んでいたり、再利用が困難な状態であったりするものは産業廃棄物として処理する必要があります。
この判断を誤ると不法投棄と見なされる可能性があるため、両者の違いを正確に理解しておくことが重要です。
産業廃棄物と一般廃棄物における汚泥の分類
汚泥は、排出元によって産業廃棄物と一般廃棄物の二つに大別されます。
廃棄物処理法で定められた特定の事業活動(例:製造業、建設業、水道業、下水道業など)に伴って排出される汚泥は、産業廃棄物に分類されます。
これには工場排水の処理で生じるものや、建設現場から出る建設汚泥などが含まれます。
一方、これらの事業活動以外から排出される汚泥、例えば浄化槽の清掃で発生する浄化槽汚泥や、し尿処理施設から出る汚泥は、一般廃棄物として扱われます。
どちらに分類されるかによって、処理責任の所在や委託すべき業者の許可の種類が異なるため、排出事業者は自社の汚泥がどちらに該当するかを正確に把握しなければなりません。
汚泥の種類を2つ紹介
汚泥は、含有される成分によって大きく「有機性汚泥」と「無機性汚 Änderungen」の2種類に分類されます。
この分類は、汚泥の性質や処理方法を決定する上で非常に重要です。
有機性汚泥は生物由来の成分を多く含み、腐敗しやすい特性を持つ一方で、堆肥化やエネルギー回収といったリサイクルに適しています。
対照的に、無機性汚泥は鉱物や金属などが主成分であり、セメント原料化や埋め立て処分が主な処理方法となります。
自社から排出される汚泥がどちらのタイプであるかを理解することは、適切な処理委託先の選定とコスト管理に直結します。
有機性汚泥
有機性汚泥とは、動植物由来の有機物を主成分とする汚泥の総称です。
主に、食品製造業の排水処理施設、下水処理場、製紙工場のパルプ廃液処理、ビルピットなどから発生します。
これらの汚泥は、栄養分を豊富に含むため微生物が繁殖しやすく、放置すると腐敗して強い悪臭を放つ原因となります。
一方で、その性質を利用してリサイクルすることも可能です。
代表的な再資源化方法には、微生物による発酵を利用した堆肥化や、メタン発酵によるバイオガス発電があります。
これにより、廃棄物を資源として有効活用し、環境負荷の低減に貢献することができます。
※参考:環境省. 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の運用に伴う留意事項について」(入手日付2023-10-06).
無機性汚泥
無機性汚泥は、金属や土砂、コンクリートくずなどの鉱物由来の無機物を主成分とする汚泥です。
代表的な発生源としては、建設工事現場(建設汚泥)、金属メッキ工場の排水処理、浄水場の沈殿池、窯業や土石製品製造業などが挙げられます。
有機性汚泥と比較して腐敗しにくく、臭気の問題は少ない傾向にありますが、重金属などの有害物質を含んでいる可能性があるため、処理には注意が必要です。
主な処理方法としては、脱水・乾燥させた後の埋め立て処分や、セメント原料、路盤材などの建設資材として再利用するマテリアルリサイクルが行われます。
処理前には成分分析を行い、有害物質の有無を確認することが不可欠です。
※参考:環境省「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の運用に伴う留意事項について」(入手日付2023-10-06).
【具体例】発生場所ごとの汚泥の種類
汚泥は、発生場所によって、含まれる成分や物理的な特性が大きく異なります。
そのため、法律上の分類だけでなく、発生場所ごとに汚泥の種類を理解することが、適切な処理方法を選択する上で重要になります。
例えば、建設現場、各種工場、オフィスビル、下水処理場など、それぞれの場所で排出される汚泥は、特有の課題と処理ニーズを持っています。
ここでは、代表的な発生場所ごとの汚泥の種類とその特徴について具体的に解説します。
建設汚泥
建設汚泥とは、建設工事現場から排出される泥状の廃棄物のことです。
具体的には、シールド工法や泥水式推進工法といった掘削工事や、杭打ち工事の際に発生する泥水、あるいは現場でコンクリートを練る際に使われる水などが処理された後に残るものを指します。
土砂(建設発生土)とは異なり、そのままでは再利用が難しく、産業廃棄物として扱われます。
主な処理方法としては、脱水処理を行って水分を減らした後に埋め立て処分されるか、固化剤を混ぜて改良土として再利用されたり、セメントの原料としてリサイクルされたりします。
建設汚泥を土砂と誤認して不適切に処理すると、不法投棄と見なされるため注意が必要です。
工場排水処理汚泥
工場排水処理汚泥は、様々な工場の生産工程から出る排水を、浄化処理する過程で発生する汚泥です。
排水に含まれる汚濁物質を凝集沈殿させたり、微生物によって分解したりした結果、汚泥として分離・回収されます。
この汚泥の性質は、工場の業種によって大きく異なり、例えば食品工場からは有機物を多く含む汚泥が、化学工場や金属加工工場からは特定の化学物質や重金属を含む汚泥が排出される可能性があります。
有害物質を含む場合は「特別管理産業廃棄物」として、より厳格な管理と処理が求められます。
そのため、処理を委託する際には、汚泥の成分を正確に分析し、情報提供することが極めて重要です。
ビルピット汚泥
ビルピット汚泥は、オフィスビルや商業施設、マンションなどの地下に設置されている排水槽(ビルピット)の清掃時に発生する汚泥を指します。
ビルピットは、建物内の厨房やトイレ、洗面所などからの排水を一時的に溜めてから公共下水道へ放流するための設備であり、その底には食品くずや油脂、土砂、固形物などが沈殿・蓄積します。
これらがビルピット汚泥であり、有機物を多く含むため、放置すると腐敗し悪臭や有害ガスの発生源となります。
建築物衛生法に基づき定期的な清掃が義務付けられており、通常はバキュームカーで吸引され、専門の処理施設へと運搬されます。
下水汚泥
下水汚泥は、家庭や事業所から排出された汚水を、下水処理場で処理する過程で発生する泥状の固形物を指します。
下水道事業を運営する地方公共団体などが排出事業者となるため、廃棄物処理法上は産業廃棄物に分類されます。
有機物を豊富に含んでおり、かつ発生量が膨大であることから、その有効活用が積極的に進められています。
主なリサイクル方法として、焼却してセメント原料や建設資材にする、発酵させて堆肥や肥料にする、メタン発酵でバイオガスを回収して発電するなど、多岐にわたる再資源化が行われており、リサイクル率が非常に高いのが特徴です。
産業廃棄物に占める汚泥の排出量
汚泥は、日本の産業廃棄物全体の中で最も大きな割合を占めています。
環境省が公表した令和4年度のデータによると、全国の産業廃棄物総排出量約3億7,383万トンのうち、汚泥の排出量は約1億5,556万トンにものぼります。
これは全体の約41.6%に相当し、2番目に多い動物のふん尿(約21.5%)を大きく引き離しています。
この膨大な量の汚泥を適切に処理し、リサイクルを進めることは、最終処分場の延命や循環型社会の構築において極めて重要な課題です。
排出事業者には、汚泥の発生抑制(リデュース)、再利用(リユース)、再生利用(リサイクル)への取り組みが強く求められています。
汚泥処理における産業廃棄物税
汚泥を含む産業廃棄物の処理にあたっては、一部の自治体で導入されている「産業廃棄物税」の存在を念頭に置く必要があります。
これは、産業廃棄物の排出抑制やリサイクルを促進し、最終処分場の延命化を図る目的で課される法定外目的税です。
課税の仕組みは自治体によって異なりますが、多くの場合、産業廃棄物を中間処理施設や最終処分場へ搬入する際に、その重量に応じて排出事業者または処理業者に課税されます。
汚泥も当然この対象となるため、事業所の所在地や処理を委託する施設の所在地にこの税制度がある場合、処理費用に税金分が上乗せされることになります。
自社が関係する自治体の条例を確認し、コスト計算に含めておくことが肝要です。
汚泥の代表的な処理方法
汚泥は水分を多く含み、そのままでは運搬や最終処分が困難なため、様々な中間処理が施されます。
これらの処理は、汚泥の容積を減らす「減量化」、有害物質を無害にする「安定化」、そして資源として再利用する「再資源化」を目的として行われます。
汚泥の性質や成分、そして最終的な処分方法に応じて、脱水、焼却、溶融、リサイクルなど多様な技術が組み合わせて用いられます。
ここでは、汚泥処理において採用される代表的な方法をいくつか紹介し、それぞれの特徴や目的を解説します。
脱水
脱水処理は汚泥処理の最も基本的な工程の一つであり、多くの場合最初に行われます。
汚泥は通常80%以上が水分であるため、この水分を取り除くことで大幅に容積を減らすことができます。
これにより運搬コストの削減や、その後の焼却、堆肥化などの処理効率を向上させる効果があります。
脱水方法には圧力をかけて水分を搾り出すフィルタープレス方式、遠心力を利用する遠心脱水方式、2枚のフィルターで挟み込むベルトプレス方式など、様々な種類の脱水機が汚泥の性質に応じて使い分けられます。
脱水後の汚泥は「脱水ケーキ」と呼ばれ固形状になります。
焼却
焼却は、脱水処理された汚泥を燃焼させることで、その容積を劇的に減らすことができる処理方法です。
有機物を多く含む汚泥の場合、焼却によって重量を数十分の一にまで減量化できます。
また、高温で燃焼させることで、病原菌などを死滅させ衛生的な状態にすると同時に、悪臭の原因物質を分解することも可能です。
焼却時に発生する熱エネルギーを回収し、発電や温水供給などに利用するサーマルリサイクルも行われています。
焼却後に残った灰(焼却灰)は、管理型最終処分場に埋め立てられるか、セメント原料などの建設資材として再利用されます。
埋め立て
埋め立ては、リサイクルや他の処理方法が困難な汚泥、あるいは焼却処理後に残った焼却灰などの最終的な処分先として行われる方法です。
最終処分場には、有害物質の流出を防ぐための遮水シートや浸出水処理施設が整備された「管理型最終処分場」などが用いられます。
ただし、日本の最終処分場の残余年数は逼迫しており、新規の建設も容易ではありません。
そのため、廃棄物処理の基本的な考え方として、埋め立て処分は最終手段と位置づけられています。
汚泥を直接埋め立てることは少なく、脱水や焼却といった中間処理によって、可能な限り減量化してから埋め立てるのが一般的です。
※参考:産業廃棄物処理事業振興財団(入手日付2023-10-06).
溶融処理
溶融処理は汚泥を1,200℃以上の超高温で加熱して溶かし、その後冷却して固化させる技術です。
このプロセスにより汚泥はガラス質の固形物である「溶融スラグ」に変わります。
溶融スラグは化学的に安定しており、有害な重金属を内部に封じ込める効果があります。
また、ダイオキシン類などの有害な有機物質は高温で分解されるため、無害化も同時に達成できます。
生成された溶融スラグは、道路の路盤材やコンクリート骨材、アスファルト合材など、建設資材として有効にリサイクルすることが可能です。
高い減容化・無害化効果がありますが、一方で、高温を維持するためのエネルギーコストが高いという側面もあります。
セメント原料化
セメント原料化は、汚泥を有効活用する代表的なリサイクル手法の一つです。
特に下水汚泥や一部の工場排水処理汚泥は、焼却するとセメントの主原料である石灰石や粘土、ケイ石と類似した成分(カルシウム、シリカ、アルミナなど)を含む灰となります。
この焼却灰を、セメント工場で原料の一部として使用することで、天然資源の採掘量を削減し、環境負荷を低減することができます。
また、廃棄物である汚泥を製品の原料として利用するため、最終処分場に埋め立てる量を減らすことにも直結します。
これは、循環型社会の形成に大きく貢献する重要なマテリアルリサイクル技術です。
堆肥化
堆肥化は、食品工場や下水処理場などから発生する有機性汚泥を、微生物の働きを利用して発酵・分解させ、肥料や土壌改良材として再資源化する方法です。
汚泥には、植物の生育に必要な窒素やリンなどの栄養分が豊富に含まれているため、これらを有効活用できます。
処理プロセスでは、汚泥に水分調整材(おがくずなど)を混ぜて空気(酸素)を送り込み、好気性微生物の活動を活発にすることで発酵を促進させます。
ただし、汚泥中に重金属などの有害物質が含まれている場合は、農地への利用が制限されるため、原料となる汚泥の安全性を事前に確認することが極めて重要です。
※参考:国土交通省「下水汚泥資源の肥料利用」(入手日付2023-10-06).
メタン発酵
メタン発酵は、有機性汚泥を酸素のない嫌気状態で微生物に分解させ、バイオガスを生成させるリサイクル技術です。
このバイオガスは、主成分がメタンであるため、燃料として利用価値が高いのが特徴です。
回収されたバイオガスは、発電機の燃料として電気を創り出したり、ボイラーで温水や蒸気を発生させたりするなど、再生可能エネルギー源として活用されます。
エネルギーを回収した後の発酵残渣は、さらに脱水処理を経て、堆肥や建設資材として利用されることもあります。
廃棄物からエネルギーと資源を回収できるため、環境負荷の低減効果が高い処理方法として注目されています。
造粒固化
造粒固化は、水分を多く含む汚泥に、セメント系の固化剤や特殊な薬剤を添加・混合し、化学反応によって固める処理方法です。
この処理により、泥状で扱いにくい汚泥を、運搬や保管が容易な粒状や土砂状の固化物に改質することができます。
また、汚泥に含まれる重金属などの有害物質が固化物の中に封じ込められ、水に溶け出しにくくなる(溶出抑制)効果も期待できます。
生成された固化物は、その強度や安全性に応じて、埋め戻し材や盛土材、路盤材などの土木・建設資材として再利用されることがあります。
脱水処理だけでは十分に水分を減らせない汚泥などに適用されることが多い技術です。
油水分離
油水分離は、油分を多く含む特殊な汚泥に対して行われる処理方法です。
例えば、ガソリンスタンドや自動車整備工場の油水分離槽に溜まる汚泥、あるいは含油廃水処理施設から発生する汚泥などが対象となります。
これらの汚泥は、水、油、固形物が混ざり合った状態になっています。
処理方法としては、遠心分離機を用いて比重の差で分離したり、加圧浮上法で油分を浮き上がらせて回収したりします。
分離された油分は再生燃料としてリサイクルされ、水分は排水処理施設で浄化されます。
残った固形物は焼却などの方法で処理されます。
廃棄物の減量化と同時に、有価物である油を回収できるメリットがあります。
汚泥の処理を業者に委託する際の注意点
汚泥の処理を外部業者に委託する際、排出事業者は単に廃棄物を引き渡すだけでなく、その処理が完了するまでの一連の過程に責任を負います。
不適切な業者を選んでしまうと、不法投棄などのトラブルに巻き込まれ、排出事業者自身が厳しい罰則を受けるリスクがあります。
そのため、業者選定はコンプライアンス遵守の観点から極めて慎重に行わなければなりません。
信頼できる業者を見極めるためには、許可の有無や処理フローの確認など、いくつかの重要なポイントを押さえておく必要があります。
許可を持つ専門業者を選ぶ
汚泥の処理を委託する上で最も基本的なことは、業者が法令に基づいた適切な許可を得ているかを確認することです。
具体的には、汚泥を収集・運搬する業者には「産業廃棄物収集運搬業許可」、処分を行う業者には「産業廃棄物処分業許可」が必要です。
これらの許可は、事業を行う区域を管轄する都道府県知事(または政令市長)から交付されます。
委託契約を結ぶ前に、必ず許可証の写しの提出を求め、許可品目に「汚泥」が含まれているか、有効期限が切れていないか、そして事業範囲(積替え保管の有無など)を自分の目で確認することが不可欠です。
複数の業者を経由する場合は、関わる全ての業者の許可を確認しなければなりません。
処理フローを確認する
許可の確認と合わせて、委託した汚泥が具体的にどのような工程を経て処理されるのか、そのフローを詳細に確認することも重要です。
収集運搬された汚泥が、どこの中間処理施設に運ばれ、どのような方法(脱水、焼却、リサイクルなど)で処理され、最終的にどこで処分されるのか、一連の流れを把握しておく必要があります。
信頼できる業者であれば、処理フロー図などを提示して明確に説明してくれるはずです。
可能であれば、実際に中間処理施設や最終処分場を訪れ、現地視察を行うことが強く推奨されます。
施設の管理状況や運営体制を直接確認することで、業者の信頼性をより正確に判断することができます。
汚泥処理に関するよくある質問
汚泥の処理は専門性が高く、日常業務で関わる機会が少ない担当者にとっては、多くの疑問が生じる分野です。
例えば、似たような性質を持つヘドロとの違いや、法律上の分類、具体的な処理実務に関する手続きなど、確認したい事項は多岐にわたります。
ここでは、汚泥処理に関して排出事業者の担当者から特によく寄せられる質問をピックアップし、それぞれについて簡潔に解説します。
これらのQ&Aを通じて、日々の廃棄物管理業務における疑問解消の一助となれば幸いです。
ヘドロの処理方法は?
ヘドロは、河川や港湾、湖沼などの水底に、動植物の死骸などが分解されて長年堆積した、有機物を多く含む黒色の泥を指します。
廃棄物処理法上では、ヘドロは「汚泥」の一種として扱われます。
そのため、処理方法は基本的に他の汚泥と同様です。
まず、ポンプやグラブ船などで浚渫して回収し、脱水処理で水分を減らします。
その後、その性質に応じて焼却、セメント原料化、あるいは建設資材として有効利用するなどの方法がとられます。
ただし、ヘドロには重金属などの有害物質が含まれている場合があるため、処理前には必ず成分分析を行い、安全性を確認した上で適切な処理方法を選択する必要があります。
汚泥の総排出量は?
環境省の最新の統計(令和4年度実績)によると、日本全国における産業廃棄物の総排出量は約3億7,383万トンです。
このうち、汚泥の排出量は約1億5,556万トンであり、全産業廃棄物の種類の中で最も多く、全体の約41.6%という大きな割合を占めています。
この数値は、前年度と比較してもほぼ横ばいで推移しており、毎年膨大な量の汚泥が発生していることを示しています。
排出量が多い背景には、下水道の普及や各種工場の排水処理技術の高度化などがあります。
このため、汚泥の減量化とリサイクルの推進は、循環型社会を実現する上での最重要課題の一つとされています。
下水汚泥は産業廃棄物に該当する?
はい、下水汚泥は産業廃棄物に該当します。
廃棄物処理法では、事業活動に伴って生じた廃棄物を産業廃棄物と定義しており、「下水道業」もその事業活動の一つと定められています。
したがって、地方公共団体などが運営する下水処理場から排出される下水汚泥は、産業廃棄物として扱われます。
一般家庭から排出されるし尿などが原料となっていますが、下水処理という事業活動を経て発生するため、一般廃棄物にはなりません。
このため、下水汚泥の処理を外部に委託する際には、産業廃棄物処理業の許可を持つ業者に依頼し、排出事業者としてマニフェスト(産業廃棄物管理票)を交付する必要があります。
汚泥処理におけるマニフェストの書き方は?
排出事業者が汚泥の処理を委託する場合、マニフェストを自らの手で交付する必要があります。紙マニフェストの基礎知識や書き方の基本を知りたい方は、「紙マニフェストの入手方法・運用の流れ・書き方をやさしく解説」を参考にしてみてください。なお電子マニフェストであれば、より効率的な運用が可能です。
汚泥処理施設とは?
汚泥処理施設とは、汚泥を減量化、安定化、無害化、または再資源化するために設置される施設の総称です。
これには多様な種類があり、代表的なものとして、汚泥の水分を取り除く「脱水施設」、有機物を燃やして灰にする「焼却施設」、高温で溶かしてスラグにする「溶融施設」、微生物の力で肥料に変える「堆肥化施設(コンポスト化施設)」などが挙げられます。
これらの施設を設置・運営するには、廃棄物処理法に基づく都道府県知事などの許可が必要であり、構造基準や維持管理基準が厳格に定められています。
排出事業者が処理を委託する際には、業者がこれらの適切な施設を保有しているかを確認することが重要です。
汚泥の比重はどれくらい?
汚泥の比重は、その組成や含水率によって大きく変動するため、一概に決まった値はありません。
一般的には、水の比重である1.0に近い、1.0から1.2程度の範囲に収まることが多いとされています。
例えば、比重が1.0であれば1立方メートルあたりの重量は1トン、1.2であれば1.2トンとなります。
しかし、土砂分を多く含む建設汚泥などは比重が1.5を超えることもあり、逆に有機物の割合が高い汚泥は1.0を下回る場合もあります。
処理費用は重量(トン)で計算されることが多いため、体積(立方メートル)で排出量を管理している場合は、実際の汚泥サンプルで比重を測定し、正確な重量を把握することがコスト管理の上で重要です。
電子マニフェストを導入するならDXE Station
収集運搬業者・処分業者の方で「排出事業者がマニフェスト登録をなかなかしてくれない……」や「マニフェスト起票時のミスが多い……」といった悩みを持つご担当者の方はいませんか?
DXE Stationをご利用いただくと代行起票機能で、排出事業者の登録を待たずにJWNETへ予約登録することができ、電子化を推進できます。
また、かんたん受注登録機能で、汚泥をはじめとする廃棄物に関するすべての受注をクラウドで一元管理することが可能です。
「排出事業者に登録を催促するのはもうイヤ……」、「紙マニフェストから解放されたい!」という方の「産廃業務のDX」をDXE株式会社が支援します。
収集運搬業者・処分業者向け事務業務軽減サービス「DXE Station」の詳しい機能・料金プランを見てみる

収運業者のお客様向け

収運・処分業者のお客様向け

収運業者と処分業者をワークフローでつなぐ

クラウドで収集運搬から
処分完了までの業務を一元化!
搬入予定の確認や、
二次マニフェストの
紐づけが簡単に!